「いよいよ施主検査だ!」となった時、「工務店で施主検査をした人達はどうやったんだろう……」と思いませんか?
そこで今回は、工務店で注文住宅をお願いした私達の場合、「どのような準備をしたのか?」・「持ち物はどうしたのか?」・「時間はどれくらい掛かったのか?」などをまとめて紹介します。
当日の流れも書いたので、興味がある人は読んでみて下さいね。
準備について

施主検査当日までに準備したのは、2つです。
- 施主検査で使う持ち物を揃える
- 自分達が確認する点をグーグルのスプレッドシートで作成⇒当日はiPadからスプレッドシートを開いて確認する
持ち物を揃えることは難しいことではなかったので、『確認する点をグーグルのスプレッドシートで作成』について説明しますね。
※持ち物については、すぐ下の方にまとめて書いています。
それでグーグルスプレッドシートで作成したものというのは、「ネットにある施主検査のチェックリストだと自分達がこだわった所を1つ1つチェックするのが難しい……。だから自分達だけの施主検査のチェックリストを作ろう!」ということです。
例えば、自分達だけの施主検査のチェックリストというのは……
- ロードバイクのラック
- 造作家具や洗面台
- 塗装ブースのための穴
ネットにある施主検査のチェックリストには記載されていないものを取り付けているため、それらを施主検査の当日に忘れずにチェック出来るようにしました!
そして施主検査のチェックリストを具体的にどのように作ったのかというと、6つのポイントがあります。
- 外と家で項目を分ける
- それぞれの部屋の項目で分ける
- 部屋の中に取り付けをお願いした物で項目を分ける(例:扉・照明・造作家具など)
- 項目を書いたら、期待する状態を書く(例:照明の型番が正しい)
- 型番やお願いした部品などが正しく取り付けられているかの確認として、スプレッドシートに参考のURLや資料を貼っておく
- 確認が完了したらチェックできるようにチェックボックスを付けておく
上のチェックリストを2人で作ると、なんと全部で157個をチェックすることが分かりました!
※157個ありますが、だいたいはどの項目も同じような検査が多いので難しくはありません。例えば、コンセントの位置が正しい・窓の開閉がスムーズに出来るなど。
チェックする所が多くて驚きましたが、施主検査の後に問題があったら困るので作って良かったですよ。
持ち物について

施主検査の持ち物はネットで調べると分かります。
ちなみに私達の場合は、iPad・設計図・住宅設備の仕様書・付箋・赤ペン・スマホです。
メジャーも持って行こうと思ったのですが、忘れました……。
それとスリッパや飲み物を持って行った方が良いと書かれているサイトもありますが、私達の場合は工務店の人が用意してくれましたよ!
持ち物がどのように活躍したのか、次で説明しますね。
当日の流れについて

当日の天気は晴れ、9時には到着していました。
9時にした理由は、2つの業者(家電と家具)に来てもらう約束をしたから。
もっと詳しく説明すると、どちらの業者も「その日の午前中は大丈夫」という連絡をもらったこと、私達が「引っ越してからすぐに使いたいから、施主検査と同じ時に全部やろう!」という考えだったからです。
※業者についての話は、すぐ下の方にまとめて書いています。
そして下のリストは当日の流れを分かりやすくまとめたものです!
- 検査できない所と残工事の説明があった
- 持ち物を準備して正解だった
- 朝早く到着して2つの業者を呼んだ
- 掛かった時間
- 工務店に伝えたのは10個
それでは1つずつ、詳しく説明します。
検査できない所と残工事の説明があった
施主検査の当日に工務店の人から、検査できない所と引き渡し後に残工事することを説明されました。
まず検査できない所というのは、取り付けていない照明があること・玄関の照明は明暗センサーなので午前中の施主検査だと確認は不可といったこと。
施主検査で全て確認するつもりだったので、検査できない所があったことを聞いた時は少し驚いてしまいました。
それと残工事というのは、1枚だけドアの寸法ミスで取り付けができず、新しいドアに交換して取り付けるというもの。
新しいドアが完成するまでに時間が掛かるらしく、引き渡し後でないと取り付けができないことを説明されましたよ。
ミスがなく、スケジュール通りに進むのが理想ですが、「家を建てるって本当に大変!!」ということを改めて感じました。
持ち物を準備して正解だった
工務店の人がマスキングテープを忘れてしまったので、付箋を用意したのは正解でした!
もちろん作成してグーグルドライブに保存しておいたスプレッドシートもiPadから開き、確認が終わったらチェックしました。
紙だとクリップボード(用箋挟)がないと書きづらく、持って行くにもかさばってしまうため、データで用意した方が楽ですよ!
それと私としては、「設計図と赤ペンを持って行ったのは良かったな」と思っています。
設計図はスプレッドシートのチェックと違い、施主検査をしている時に見つけたキズや汚れなどを赤ペンで書いていきます。
※設計図は住宅設備の仕様書と一緒になっていたので、データではなく、そのまま持って行きました。
設計図は黒色をたくさん使っているので、気になった所を赤ペンで書くと分かりやすく、文章やリストでまとめるよりも分かりやすいですよ。
あとはスマホで撮影しておけば、しっかりと直してもらったか確認できます。
そしてメジャーについてですが、「持って行くべきだったかも……」と思っています。
しかしメジャーで測ったとしても、そもそもお願いをしたサイズを間違えている可能性があります……。
引渡し後の話を少し書きますが、お願いした高さの机を作ってもらったら、「そもそもお願いした高さが間違っていた」ということがありました。
※高さが間違っていた机は、引渡し後に直してもらいました。
つまり、「測ったから大丈夫」ではなく、「自分達が欲しい家具や家電などのサイズは合っているのか?」という所から確認した方が良いということです。
あとから直すのは大変なので、私達のような間違いをしないようにして下さいね。
朝早く到着して2つの業者を呼んだ
呼んだのは、冷蔵庫の搬入経路を確認する電気屋とウッドブラインドのために窓を採寸する業者です。
冷蔵庫の話に興味ある人は下の記事からどうぞ!
それで工務店から聞いたのですが、「工務店と関係がない業者を呼ぶのは基本的にはNG」だそうです。
ただ私達の場合、工務店がOKしてくれました。
理由は、工務店も施主のことを見て様々なことを判断(工務店で働いている人達も人間ですからね)していて、私達は『困った施主』と思われていなかったから。
私としては、工務店とは良い関係でいたいので、困った施主に見られてなくて安心しました!
それと、「ハウスメーカーの場合は関係がない業者は呼べない」ということも工務店が教えてくれました。
なかなか聞けない話なので、「臨機応変に対応してもらえるのは工務店の魅力だよね!」と思いましたよ。
掛かった時間
9時には到着をして、施主検査と2つの業者を呼び、掛かったのは約3時間。
1時間以上電車に乗らないといけないので、朝が早くて大変でしたが、お昼には終わっていたので午後はゆっくり家に帰りました。
2つの業者がそれぞれ掛かった時間は、冷蔵庫の搬入経路の確認は約10分、ウッドブラインドの採寸は約30分。
どのような動きをしていたかというと、業者がいた時は検査を止めて、工務店の人は「何かあったら声を掛けて下さい」と言って事務作業をしていました。
だから工務店の人が私達とずっと一緒にいることはなかったです。
ちなみに業者の出入りがあったため、私も夫も少々ドタバタしていたというのはあります。
施主検査だけに集中したい人は、業者は別の日に呼ぶようにした方が良いかもしれません。
工務店に伝えたのは10個
施主検査をして、工務店に伝えたのは10個。
どのようなことを伝えたのか、その一部を紹介します。
- 玄関ホールのキズ
- 造作家具の引き出しの不具合
- 洗面化粧台の引き出しの不具合
- シューズボックスでお願いしたオプションが付いていなかった
上のような内容で、工務店の人からは「引渡し前には直せます」と言ってくれたので安心しました。
ネットで施主検査のことを調べた時は、「キズ・汚れ・間違いなどがたくさんあって大変だった」といった内容が多く、「施主検査をして気になる所がたくさんあったらどうしよう……」とマイナスに考えていた所があったので、実際に施主検査をしてみたら違ったのでホッとしましたよ。
施主検査の当日は少々ドタバタでしたが、大きなトラブルはなく、午前中に終わって良かったです!
これから住む家をじっくりと検査できる貴重な時間なので、しっかりと準備して後悔しないようにして下さいね。



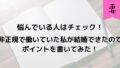
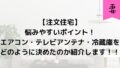
コメント